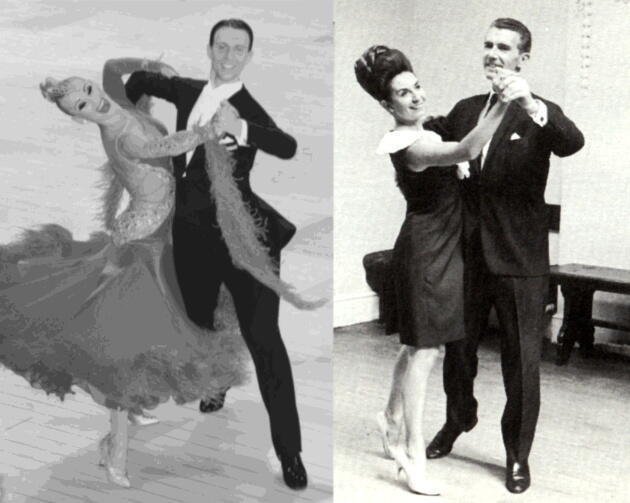| みらくるダンス .com |
| ***** |
| サークルかがやき ダンス練習会 |
| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |
| ***** |
| 管理人へのメール はこちらから |
| ***** |

|

|

|

|
| ***** |

|

|
| みらくるダンス .com |
| ***** |
| サークルかがやき ダンス練習会 |
| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |
| ***** |
| 管理人へのメール はこちらから |
| ***** |

|

|

|

|
| ***** |

|

|
|
> 超!4スタンス理論 > 投稿843 |
【ブログ記事】 管理人が投稿した記事と、読者から寄せられたコメントです。
2021/05/17(月) 02:23:21
| カテゴリー[ 超!4スタンス理論 ]
| 「社交ダンスの理論」は「4スタンス理論」を越えている。 社交ダンスの「いろはのい」 一方、足の裏の「ヒール側」にパワーラインを作るBタイプ(写真左)は、 だがしかし、腕や掌(てのひら)に変化を与えたり これは推測なのですが、 例え、腕、ハムストリングスを使えば、 歴史的に見て、おそらく、 実際、どうなんだろうね。 時代とともに、 でも、それ以前に、 先生が理解できていなければ、
なぜなら、AタイプとBタイプでは、
| 
この投稿へのコメントは 無効 です。 コメント(0 件)を読む・新たなコメントをする |
→ブログのトップページ(最新8件を表示)へ
→カテゴリー〔超!4スタンス理論〕の投稿(すべて)を表示
→前〔投稿842 2021/05/17〕: 飲食自粛は、効果有り!
→次〔投稿844 2021/05/18〕: PCR検査の正確さ
以前のページに戻る ・↑このページの先頭へ
|
このブログの管理人 (さんぞう)へのメール は、〔こちら〕から このブログの管理人(さんぞう) へのメールは、〔こちら〕から |