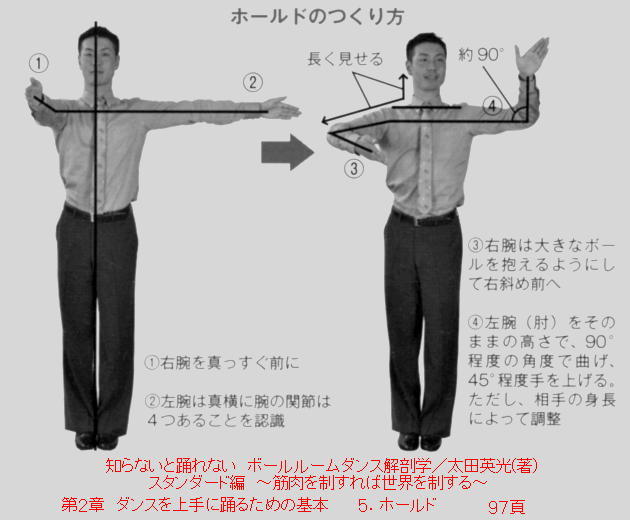| みらくるダンス .com |
| ***** |
| サークルかがやき ダンス練習会 |
| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |
| ***** |
| 管理人へのメール はこちらから |
| ***** |

|

|

|

|
| ***** |

|

|
| みらくるダンス .com |
| ***** |
| サークルかがやき ダンス練習会 |
| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |
| ***** |
| 管理人へのメール はこちらから |
| ***** |

|

|

|

|
| ***** |

|

|
|
> 超シンプルに考える > 投稿710 |
【ブログ記事】 管理人が投稿した記事と、読者から寄せられたコメントです。
2021/03/06(土) 04:33:46
| カテゴリー[ 超シンプルに考える ]
| このタイトルだと、見る人少ないから、 相撲とか、弓道とか、アーチェリーには、 youtube とかで検索すると、ゴルフの説明が沢山出てくるけど 日本の社交ダンスのスタンダードのホールドにおいては、 これを考える目的で、2つを比較!
一つめの考え方は、 要するに、社交ダンスを踊る時に、 どちらを、「社交ダンスの基礎」と考えるか 太田先生の本を読めば、日本の社交ダンス
| 
この投稿へのコメントは 無効 です。 コメント(0 件)を読む・新たなコメントをする |
→ブログのトップページ(最新8件を表示)へ
→カテゴリー〔超シンプルに考える〕の投稿(すべて)を表示
→前〔投稿709 2021/03/05〕: 感染者ゼロは 実現可能
→次〔投稿711 2021/03/06〕: なかなか いい感じ!
以前のページに戻る ・↑このページの先頭へ
|
このブログの管理人 (さんぞう)へのメール は、〔こちら〕から このブログの管理人(さんぞう) へのメールは、〔こちら〕から |